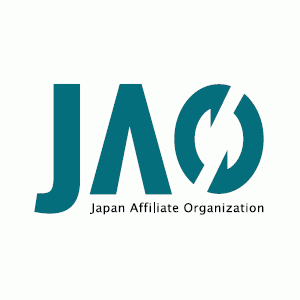「織組織」の話に登場する白黒のマス目が並んだ図(方眼の組織図)の読み方
公開日: | 最終更新日: 2018/06/06 読書・学び
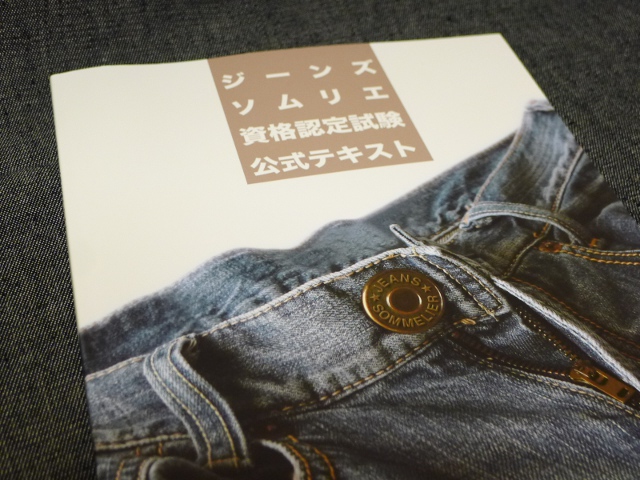
ジーンズソムリエ公式テキストの「織組織」の項がよくわからないので、ネットでいろいろ調べていたら、白黒のマス目が並んだ図が出てきてますます迷宮に迷い込んだ感じに。
※こんな感じ ⇒ 「織組織」画像検索結果
たいていの図には解説がついていますが、図の読み方はわかっているものとしてその組織の特徴が説明されているので、なんとなーくニュアンスはつかめるものの正しく理解できているか確信がもてません。
で、なんとかこのあたりの知識不足を補いたいなぁと思っていたんですが、試験対策のために買った本の中にその答えがあったので以下にまとめておきます。
【織物組織の表し方についての基礎知識】
● 織物:
たて糸とよこ糸を原則として互いに直角かつ上下に交錯させて平面のシートにしたもの。布地としては、織物のほかにも、編物、フェルトなど様々な種類がある。
● 織物組織:
織物のたて糸とよこ糸の交差の仕方、たて糸がよこ糸の上になるか下になるかの組み合わせ方を「組織」という。
● 組織図:
たて糸とよこ糸の組み合わせ方を「意匠紙」という方眼紙を用いて表したもの。隣りあうタテ罫線どうしの間がそれぞれたて糸1本、ヨコ罫線間の空間がそれぞれよこ糸1本を表している。
原則として、たて糸がよこ糸の上になっている(たて糸が浮いている)マス目を黒、たて糸がよこ糸の下になっている(たて糸が沈んでいる)マス目を白で表す。
● 組織点:
たて糸とよこ糸が交差している点のこと。
● 完全組織:
織物の組織は一区間の組織をくり返して構成されているが、この最少区間を完全組織という。
【参考文献】
- 繊維の種類と加工が一番わかる しくみ図解
(p.64~)
- テキスタイル用語辞典
(「基礎用語」の章)
- ファッションのための繊維素材辞典
ちなみに、
ソムリエ公式テキストには組織図ではなく、織物組織が見える拡大写真(?)が掲載されていますが(p.31~32)、この写真でも黒っぽい方がたて糸のようです。
綾織りの組織写真がデニム生地だとしたら、たて糸はインディゴの色ということになりますね。
スポンサード・リンク
関連記事
-
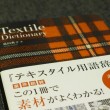
スラブ糸とネップ糸の違いを調べた。
ジーンズソムリエ公式テキスト(p.34)の「シャンブレー」の説明に出てくる「スラブ糸」と「ネップ糸」
-

ポリエステルとポリウレタンの違い、というか、覚えるためのキャラわけ的な・・・
なんだか本筋からだいぶ外れてきてますが、ジーンズソムリエ公式テキストに出てくる「ポリエステル
-

藍染め・インディゴ染色における「酸化」と「還元」について調べた。
化学の記憶がなさすぎて泣きそうですが、がんばります。(高校理科は「地学」選択だったけど、たしか1年生
-

読書感想: 日本における産地綿織物業の展開(阿部武司, 東京大学出版会)
もうすぐ年末ですね。バタバタ過ごしつつ本を読んだりしています。 今日は、11月に読んだ
-
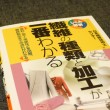
繊維製品におけるデニム生地の位置づけをざっくりまとめてみた。
繊維の種類と加工が一番わかる しくみ図解を読みました。 この本の中でデニム(綿布)に関
-
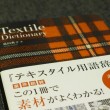
紡績と製糸の違いを学んだ。
ジーンズソムリエ公式テキストを読みながら、「紡績っていうと難しい感じがするけど糸を作ることだ
-
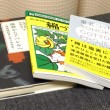
ジーンズ関連で最近買った本・借りた本、いままでに読んだ本とかとか。
ジーンズに関連して勉強したいことはまだまだ山のようにあるんですが、まとまった時間を確保し
-

ジーンズに使われる生地を分類してみた。
ジーンズに使われる生地はさまざま。 たとえばカラージーンズなどでは、デニム以外の色んな生地が使われて
-
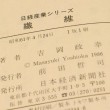
読書感想: 日経産業シリーズ 繊維(吉岡政幸, 日本経済新聞社)
古い本ですが(1986年出版)、あまり知らない時代の話だったのと(や、もちろん生まれてはいる
-

ジーンズの製造工程についての勉強、はじめました。
ジーンズソムリエ資格認定試験に申し込み、公式テキストでジーンズの製造工程についての勉強をはじ